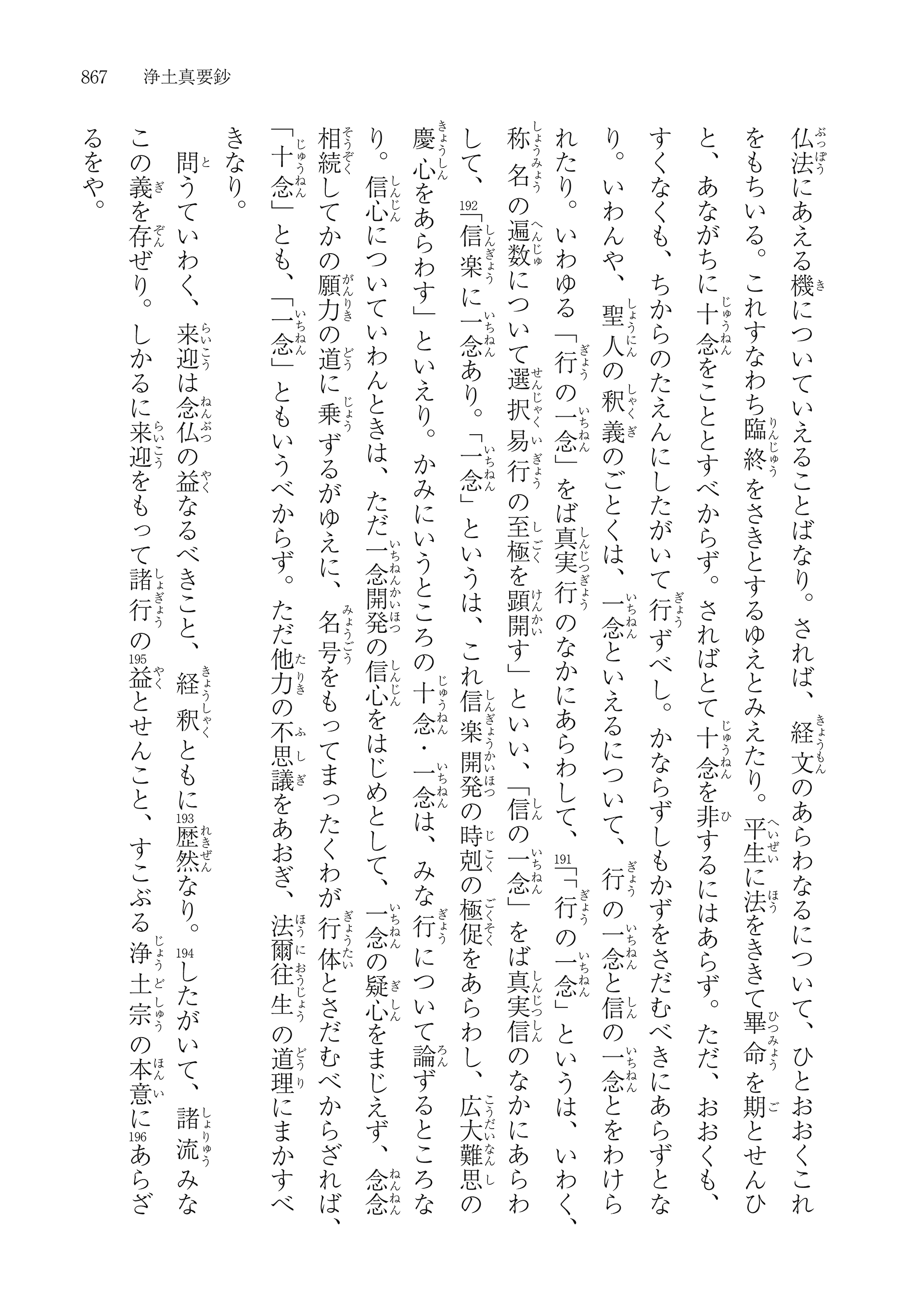- あ
- あ
- あ
- ゴシック
- 明朝
- あ
- あ
- あ
仏法にあえる機についていえることばなり。されば、経文のあらわなるについて、ひとおおくこれをもちいる。これすなわち臨終をさきとするゆえとみえたり。平生に法をききて畢命を期とせんひと、あながちに十念をこととすべからず。さればとて十念を非するにはあらず。ただ、おおくも、すくなくも、ちからのたえんにしたがいて行ずべし。かならずしもかずをさだむべきにあらずとなり。いわんや、聖人の釈義のごとくは、一念といえるについて、行の一念と信の一念とをわけられたり。いわゆる「行の一念」をば真実行のなかにあらわして、「「行の一念」というは、いわく、称名の遍数について選択易行の至極を顕開す」といい、「信の一念」をば真実信のなかにあらわして、「信楽に一念あり。「一念」というは、これ信楽開発の時剋の極促をあらわし、広大難思の慶心をあらわす」といえり。かみにいうところの十念・一念は、みな行について論ずるところなり。信心についていわんときは、ただ一念開発の信心をはじめとして、一念の疑心をまじえず、念念相続してかの願力の道に乗ずるがゆえに、名号をもってまったくわが行体とさだむべからざれば、「十念」とも、「一念」ともいうべからず。ただ他力の不思議をあおぎ、法爾往生の道理にまかすべきなり。
問うていわく、来迎は念仏の益なるべきこと、経釈ともに歴然なり。したがいて、諸流みなこの義を存ぜり。しかるに来迎をもって諸行の益とせんこと、すこぶる浄土宗の本意にあらざるをや。