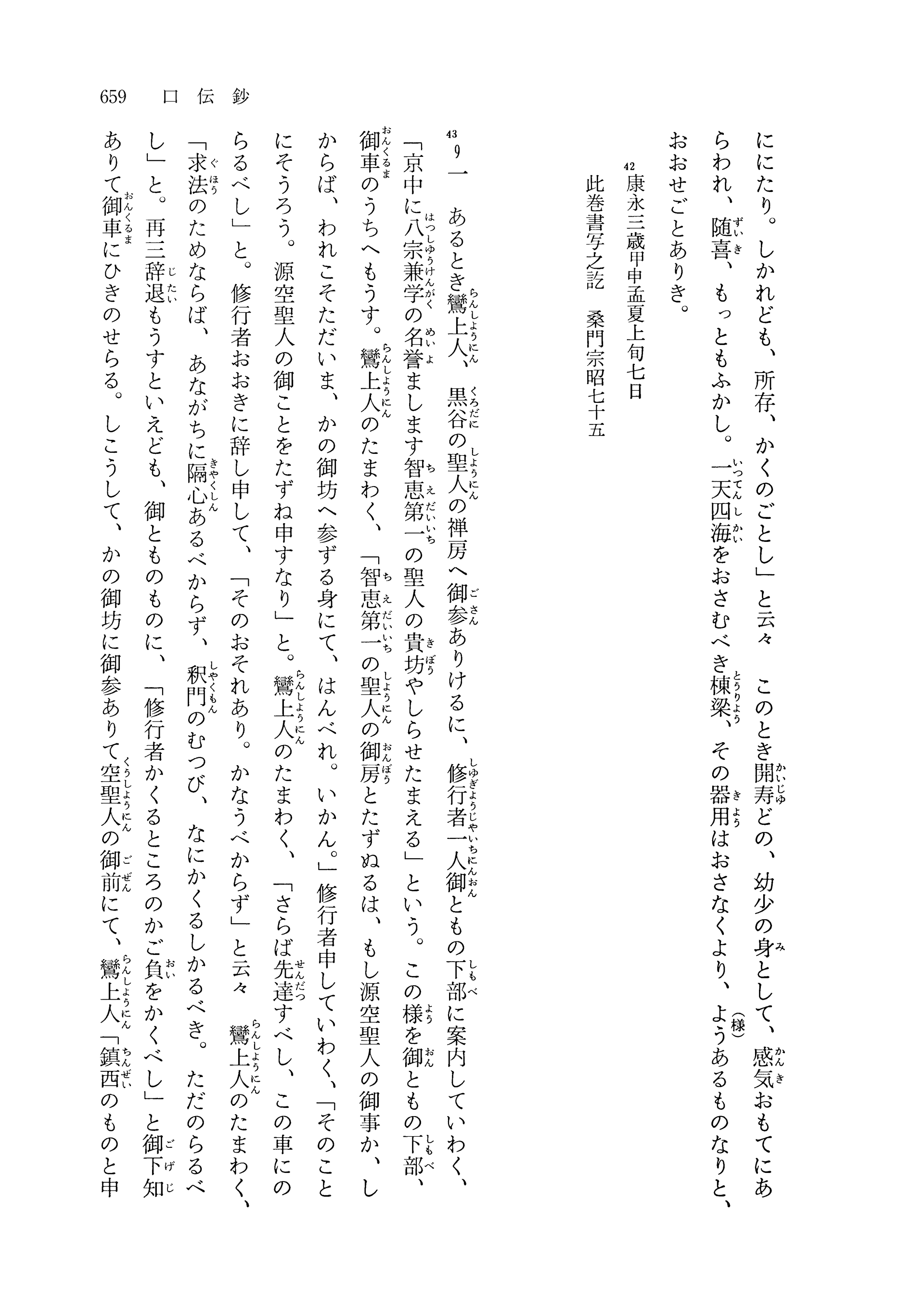-
659頁
表示設定
ブックマーク
表示設定
- あ
- あ
- あ
- ゴシック
- 明朝
- あ
- あ
- あ
テキスト情報
本文
画像情報
画像情報
ににたり。しかれども、所存、かくのごとし」と云々 このとき開寿どの、幼少の身として、感気おもてにあらわれ、随喜、もっともふかし。一天四海をおさむべき棟梁、その器用はおさなくより、ようあるものなりと、おおせごとありき。
康永三歳 甲申 孟夏上旬七日
此巻書写之訖 桑門宗昭 七十五
9一 あるとき鸞上人、黒谷の聖人の禅房へ御参ありけるに、修行者一人御ともの下部に案内していわく、「京中に八宗兼学の名誉まします智恵第一の聖人の貴坊やしらせたまえる」という。この様を御ともの下部、御車のうちへもうす。鸞上人のたまわく、「智恵第一の聖人の御房とたずぬるは、もし源空聖人の御事か、しからば、われこそただいま、かの御坊へ参ずる身にて、はんべれ。いかん。」修行者申していわく、「そのことにそうろう。源空聖人の御ことをたずね申すなり」と。鸞上人のたまわく、「さらば先達すべし、この車にのらるべし」と。修行者おおきに辞し申して、「そのおそれあり。かなうべからず」と云々 鸞上人のたまわく、「求法のためならば、あながちに隔心あるべからず、釈門のむつび、なにかくるしかるべき。ただのらるべし」と。再三辞退もうすといえども、御とものものに、「修行者かくるところのかご負をかくべし」と御下知ありて御車にひきのせらる。しこうして、かの御坊に御参ありて空聖人の御前にて、鸞上人「鎮西のものと申