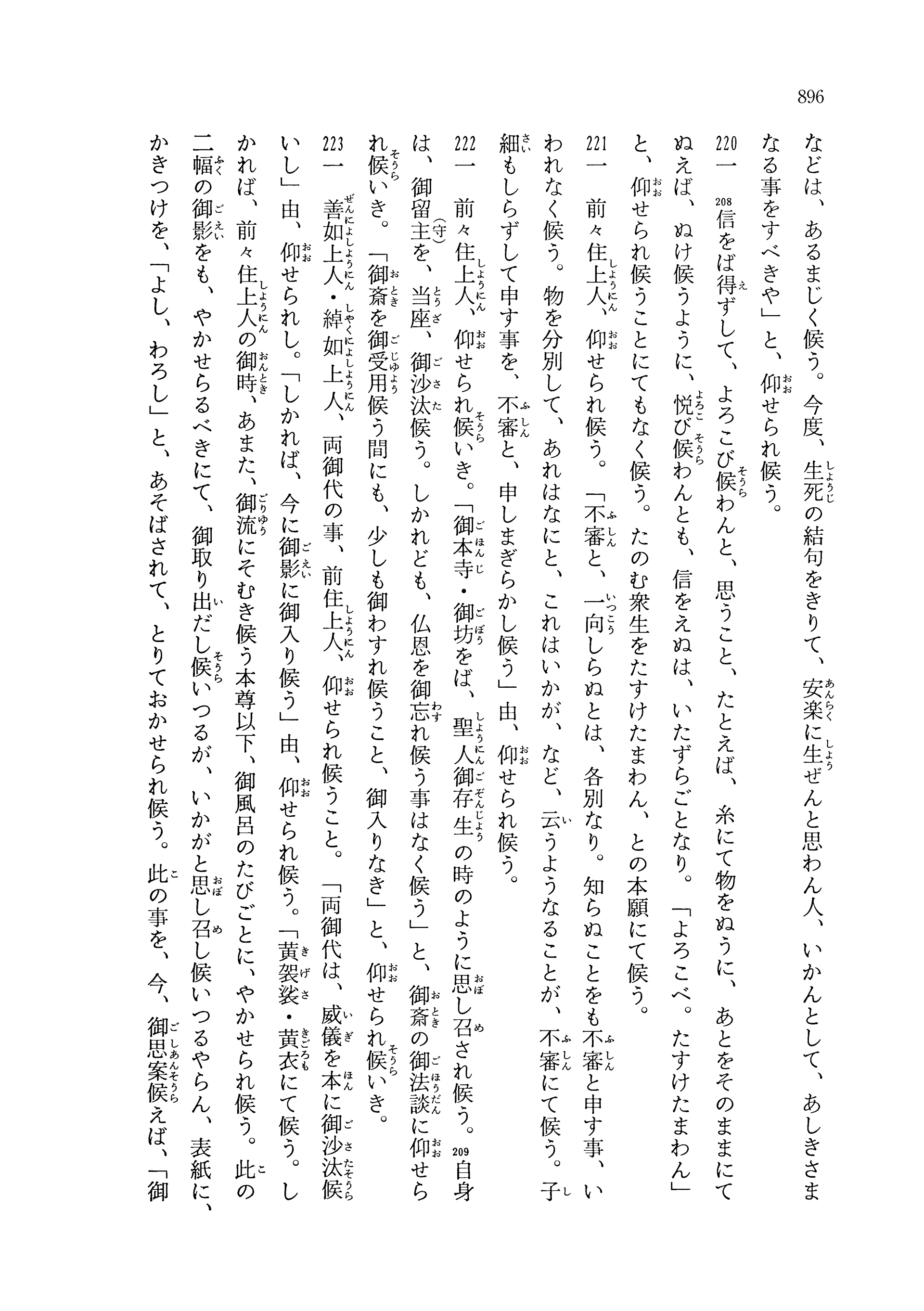- あ
- あ
- あ
- ゴシック
- 明朝
- あ
- あ
- あ
などは、あるまじく候う。今度、生死の結句をきりて、安楽に生ぜんと思わん人、いかんとして、あしきさまなる事をすべきや」と、仰せられ候う。
220一 信をば得ずして、よろこび候わんと、思うこと、たとえば、糸にて物をぬうに、あとをそのままにてぬえば、ぬけ候うように、悦び候わんとも、信をえぬは、いたずらごとなり。「よろこべ。たすけたまわん」と、仰せられ候うことにてもなく候う。たのむ衆生をたすけたまわん、との本願にて候う。
221一 前々住上人、仰せられ候う。「不審と、一向しらぬとは、各別なり。知らぬことをも不審と申す事、いわれなく候う。物を分別して、あれはなにと、これはいかが、など、云うようなることが、不審にて候う。子細もしらずして申す事を、不審と、申しまぎらかし候う」由、仰せられ候う。
222一 前々住上人、仰せられ候いき。「御本寺・御坊をば、聖人御存生の時のように思し召され候う。自身は、御留主を、当座、御沙汰候う。しかれども、仏恩を御忘れ候う事はなく候う」と、御斎の御法談に仰せられ候いき。「御斎を御受用候う間にも、少しも御わすれ候うこと、御入りなき」と、仰せられ候いき。
223一 善如上人・綽如上人、両御代の事、前住上人、仰せられ候うこと。「両御代は、威儀を本に御沙汰候いし」由、仰せられし。「しかれば、今に御影に御入り候う」由、仰せられ候う。「黄袈裟・黄衣にて候う。しかれば、前々住上人の御時、あまた、御流にそむき候う本尊以下、御風呂のたびごとに、やかせられ候う。此の二幅の御影をも、やかせらるべきにて、御取り出だし候いつるが、いかがと思し召し候いつるやらん、表紙に、かきつけを、「よし、わろし」と、あそばされて、とりておかせられ候う。此の事を、今、御思案候えば、「御