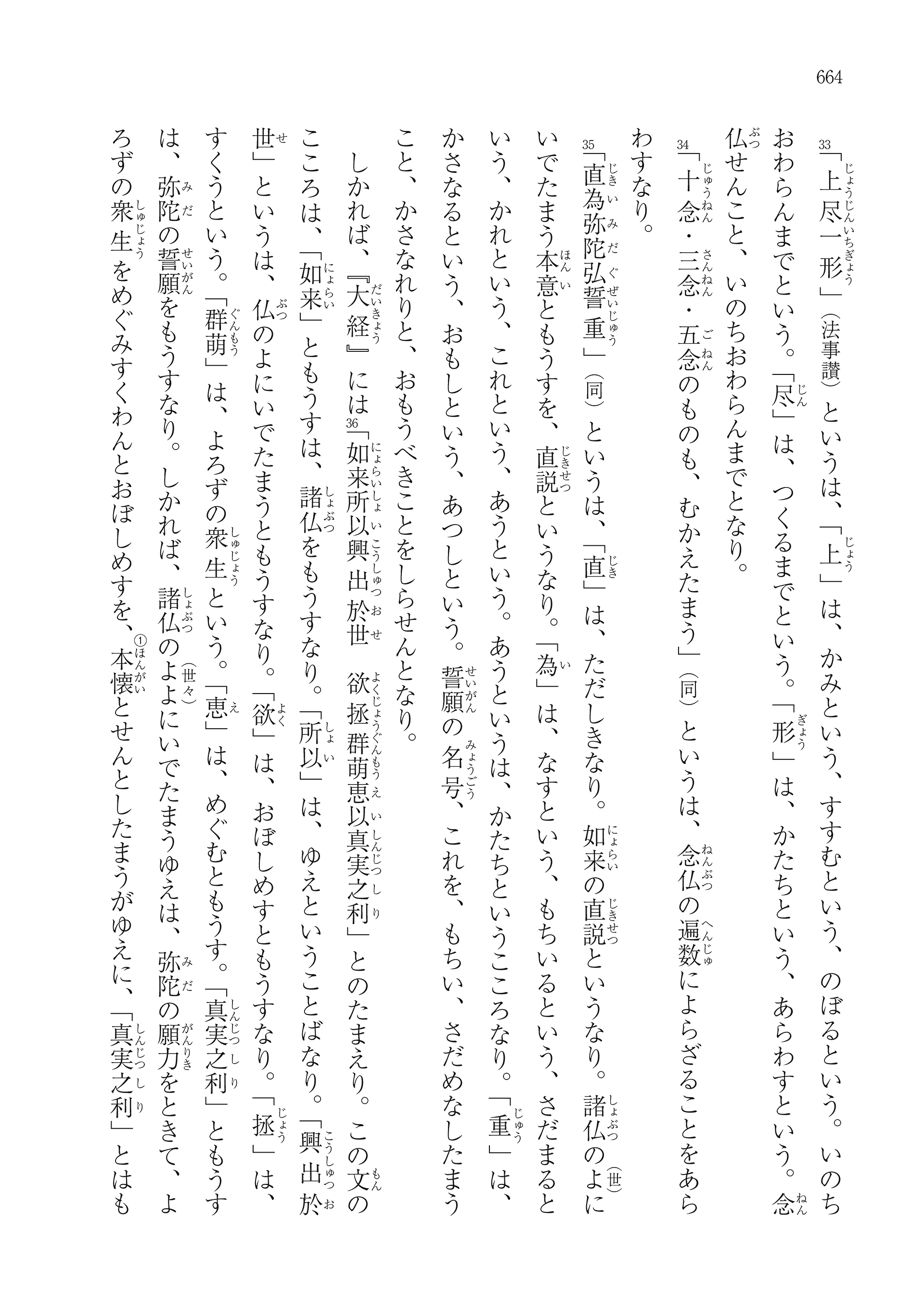- あ
- あ
- あ
- ゴシック
- 明朝
- あ
- あ
- あ
「上尽一形」(法事讃)というは、「上」は、かみという、すすむという、のぼるという。いのちおわらんまでという。「尽」は、つくるまでという。「形」は、かたちという、あらわすという。念仏せんこと、いのちおわらんまでとなり。
「十念・三念・五念のものも、むかえたまう」(同)というは、念仏の遍数によらざることをあらわすなり。
「直為弥陀弘誓重」(同)というは、「直」は、ただしきなり。如来の直説というなり。諸仏のよにいでたまう本意ともうすを、直説というなり。「為」は、なすという、もちいるという、さだまるという、かれという、これという、あうという。あうというは、かたちというこころなり。「重」は、かさなるという、おもしという、あつしという。誓願の名号、これを、もちい、さだめなしたまうこと、かさなれりと、おもうべきことをしらせんとなり。
しかれば、『大経』には「如来所以興出於世 欲拯群萌恵以真実之利」とのたまえり。この文のこころは、「如来」ともうすは、諸仏をもうすなり。「所以」は、ゆえということばなり。「興出於世」というは、仏のよにいでたまうともうすなり。「欲」は、おぼしめすともうすなり。「拯」は、すくうという。「群萌」は、よろずの衆生という。「恵」は、めぐむともうす。「真実之利」ともうすは、弥陀の誓願をもうすなり。しかれば、諸仏のよよにいでたまうゆえは、弥陀の願力をときて、よろずの衆生をめぐみすくわんとおぼしめすを、本懐とせんとしたまうがゆえに、「真実之利」とはも